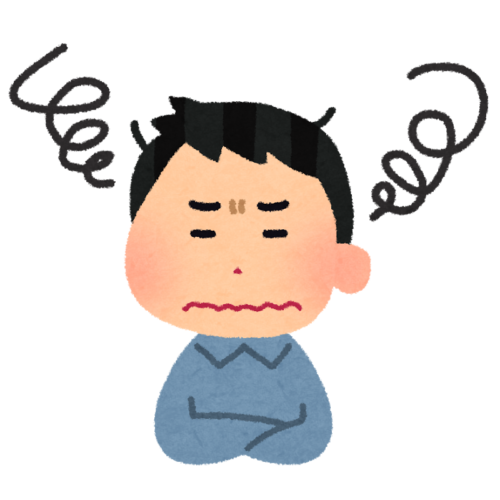こんな悩みを解決できる記事を用意しました!
記事前半では免税事業者の消費税について、後半では消費税を請求する場合の注意点や免税事業者はどうするべきか解説するので、ぜひ参考にしてくださいね!
目次
インボイス制度とは?
消費税が請求できるかどうかの前に、そもそもインボイス制度について知りたい方のために簡単に説明しておきます。
今までの制度では消費税の仕入税額控除は基本的に請求書等があれば控除できました。
ですが、インボイス制度が始まると税務署へ登録した事業者が発行する適格請求書(インボイス)がないと仕入税額控除できなくなります。
消費税の計算は、「売上に係る消費税ー仕入に係る消費税=納付額」です。
仕入税額控除とは「仕入に係る消費税」として「売上に係る消費税」から差し引ける消費税部分のことです。
これができなくなってしまうと、自分が仕入で支払った消費税を売上に係る消費税から引けませんので、消費税の納税額が増えてしまいます。
インボイスと現行の請求書の大きな違いは登録番号です。
インボイスの発行は税務署への登録が必要ですが、その際に発行される登録番号を請求書等へ記載する必要があります。
インボイス制度ではインボイスとして登録番号の記載された請求書等がないと仕入税額控除ができないので、インボイスの重要性がすごく高いといことですね。
インボイス制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にどうぞ。
-

-
インボイス制度における課税事業者の登録って?という方向けに解説
悩んでいる人 ・インボイス制度の登録ってそもそも何? ・インボイス制度って登録しないといけないんだよね? ・そもそもどうやって登録するの? 光實 こんにちは、公認会計士・税理士の光實(みつざね)です。 ...
免税事業者は消費税を請求できる?
結論から先に言ってしまうと、免税事業者はインボイス制度が始まっても消費税を請求できます。
インボイス制度に変わっても免税事業者は消費税を請求してはいけないというような規定はありません。
なので、今までと同じように消費税を請求書へ記載して請求すること自体は可能です。
また後程詳しく説明しますが、免税事業者との取引においては、消費税の仕入税額控除の経過措置も認められています。
これは、免税事業者からの取引についても一部仕入税額控除を認める仕組みで、段階的に減らされていきます。
免税事業者と取引先の双方でインボイス制度への移行のストレスを緩和する趣旨によるものですね。
免税事業者が消費税を請求する場合の注意点
ただし、インボイス制度は免税事業者だけの立場で考えると失敗します。
取引先にも影響を与える可能性があるためです。
取引先は仕入税額控除ができない
最初に説明しましたが、インボイス制度はインボイスがないと仕入税額控除ができません。
なので、免税事業者と取引をする会社は仕入税額控除がとれなくなります。
例で考えてみます。
B社はA社から商品を仕入れ、一般の消費者へ販売しているとします。
A社
↓商品100円+消費税10円
B社
↓商品150円+消費税15円
一般の消費者
①A社がインボイス発行事業者の場合のB社の納税額
15円-10円=5円
②A社が免税事業者の場合のB社の納税額
15円-0円=15円
このように、免税事業者との取引では仕入に係る消費税10円が控除できなくなります。
なので、免税事業者が今まで通り消費税を請求してくると取引先は損をするということですね。
取引が減る又は、無くなる可能性がある
免税事業者と取引をすると損をする可能性があるとなると、取引先はどうするか。
当然取引を見直したいと思いますよね?
なので、取引自体が減る又は価格交渉される可能性がありますし、下手をすると取引がなくなってしまうこともあるかもしれません。
買い手側の立場が強い場合における不当な要求は違法となる可能性がある
売り手よりも買い手の立場が強い場合、値下げ交渉や、消費税の転嫁の拒否、適格請求書発行事業者になるように勧めるなどの話がでてくるかもしれません。
そして、断れば取引を停止するというように言われるケースがあるかもしれません。
ですが、その場合、買い手の立場を利用して売り手に対して不当な要求をしているとして、独占禁止法や下請法上問題になる可能性があります。
これは、価格交渉などをしてはいけないということではないので、注意してください。
あくまで、一方的に買い手が自身の立場を利用して、断ることのできない売り手に対して不利益を与える行為が問題になるよということですね。
免税事業者はどうすればいいの?
じゃあ、免税事業者はインボイス制度が始まったらどうすればいいのか?
という話しですが、こちらについても解説しておきます。
取引先との価格交渉に応じる
インボイス制度が始まっても免税事業者でいる場合、取引先はどうしても免税事業者と取引することで損をする(消費税の納税額が増える)可能性があります。
なので、取引を継続していく場合には、やはり価格交渉は必要になると思います。
免税事業者の立場からすると関係ないことになりますが、インボイスがないと取引先は消費税の仕入税額控除が取れない分、手取りが減るわけですから、免税事業者だけ知らんぷりすることは難しいですよね。
継続して取引をする事業者であればなおさら、その部分についてお互いが納得できるように価格交渉するのが妥当ということになります。
経過措置を利用する
免税事業者との取引には経過措置が認められています。
インボイス制度が始まっていきなり全額仕入税額控除がとれなくなると、全ての事業者への影響が大きすぎるので、段階的に控除額が減る仕組みにしています。
具体的には以下のようになります。
| 期間 | 控除割合 |
| 令和5年10月1日から令和8年9月30日 | 80%控除 |
| 令和8年10月1日から令和11年9月30日 | 50%控除 |
| 令和11年10月1日以降 | 仕入税額控除不可 |
なので、例えば1,000円の物を仕入れて消費税を100円払った場合、相手が免税事業者であれば、当初3年間は80円まで控除可能です。
そしてその後3年間は50円まで控除額が減り、最終的には控除額0円となり段階的に控除できる額が減っていきます。
つまり、インボイス制度が始まってから最初の3年間は仕入税額控除が80%はとれます。
なので、この期間は免税事業者のままでいき、それまでにその後も免税事業者でいくのか、課税事業者かつ適格請求書発行事業者になるのかというのを検討するのも1つの手段になります。
課税事業者かつ適格請求書発行事業者となりインボイスの発行をする
インボイスの発行ができるようになれば、取引先が損することはありません。
なので、今まで通りの取引を行うことが可能です。
ただし、適格請求書発行事業者は課税事業者なので、今まで必要なかった消費税の申告や納税が必要になります。
インボイスの発行ができる適格請求書発行事業者になるかどうかは、取引先に与える影響や、売上への影響、納税額がどの程度になるのかを考えて検討する必要があります。
このあたりの検討方法について詳しくは、こちらの記事に記載していますので、参考にしてください。
-

-
インボイス制度が始まっても免税事業者のままでいたい人に向けて解説
悩んでいる人 ・インボイス制度後も免税事業者のままではだめなの? ・免税事業者のままでもインボイスの発行もできる? ・免税事業者のままのデメリットってあるの? 光實 こんにちは、公認会計士・税理士の光 ...
まとめ
まとめます。
ポイント
・免税事業者はインボイス制度後も消費税を請求できる
・免税事業者と取引した場合、取引先は仕入税額控除ができない
・免税事業者のままでいる場合、取引先への影響も考慮(価格交渉等)する必要がある
・インボイス制度には経過措置があるため、経過措置を利用しつつ、適格請求書発行事業者になることを検討することもできる
免税事業者はインボイス制度についてどのように対応していくかは、事業者ごとに答えは異なります。
まわりの免税事業者が適格請求書発行事業者になったからといって、自分もそれが適しているとは限りません。
この記事なども参考にしつつ、自身に適しているのはどういった業態かを検討してみるのがいいと思います。
必要であれば専門家への相談も検討しましょう。