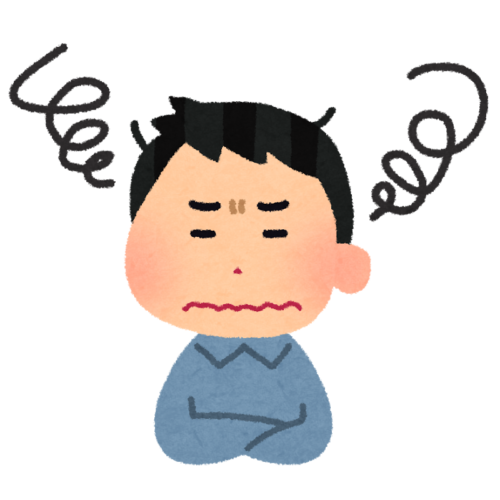こんにちは、公認会計士・税理士の光實(みつざね)です。
こんな悩みを解決できる記事を用意しました!
記事前半では保存しないといけない請求書等について、後半では保存しなくてもいいケースを紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね!
目次
仕入税額控除とは
インボイス制度は仕入税額控除のお話しがメインになるので、まずは仕入税額控除を説明しておきますね。
消費税は、商品やサービスの提供を受ける消費者が支払う税金ですが、事務負担の問題などにより事業者が代わりに納めています。
計算方法を簡単に説明すると、事業者が①消費者などに売って預かった消費税と②仕入れにより支払った消費税を差しひいて、計算します。
その時に、事業者が仕入により支払った消費税として差し引ける部分が仕入税額控除と言われる部分です。
| ①消費者などに売って預かった消費税ー②仕入れにより支払った消費税(仕入税額控除)=納める消費税 |
なんで請求書等を保存しないといけないのか?
インボイス制度化での仕入税額控除の要件は、帳簿と適格請求書等の保存です。
これらの要件を充たしていないと仕入税額控除が認められません。
仕入税額控除は多く取れた方が、納める側にとっては有利です。
なので、インボイス制度では請求書等(適格請求書等)をちゃんと保存しておく必要があります。
適格請求書等ってなに?
仕入税額控除をするためには、適格請求書等を保存しないといけないのはわかったけど、これってどいういうものなの?
という疑問があると思います。
なので、適格請求書についても説明しておくと。
適格請求書の様式は法令や通達で定められていません。
必要な記載事項があれば、手書きなどでもよく、名称も請求書や領収書など決まりはありません。
適格請求書の記載事項は?
適格請求書の記載事項として、必要な記載事項が6つほどあります。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した税抜きまたは税込み対価の額および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
赤字で記載した箇所は、現行制度からの変更点になります。
大きく変更している部分としては、登録番号です。
これは、適格請求書発行事業者として税務署へ登録申請した事業者に付与される番号です。
この登録をしていないと、適格請求書発行事業者になれませんのでご注意ください。
請求書等の保存ってなにを保存するの?
保存が必要となる請求書等としてどんなものがあるか見ておきたいと思います。
①売り手が交付する適格請求書または適格簡易請求書
②買い手が作成する仕入明細書等(適格請求書の記載事項があり、相手方の確認を受けているもの。)
③卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡について、受託者から交付を受ける書類
④農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける書類
それぞれ電磁的記録(電子データ)での保存も認められています。
順番に解説します。
①売り手が交付する適格請求書または適格簡易請求書
適格請求書については、上で説明してきたので、ここでは、適格簡易請求書の説明をしておきたいと思います。
適格簡易請求書は、小売業や飲食店業など、不特定多数の人とやり取りする業種について、発行が認められている請求書です。
内容としては、適格請求書で記載が必要な、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の省略などが認められています。
こちらの記事にさらに詳しく書いていますので参考にどうぞ。
-

-
適格請求書と適格簡易請求書の違いって何?図でわかりやすく解説!
悩んでいる人 ・適格請求書と適格簡易請求書って何が違うの? ・誰が発行できるの? ・免税事業者も発行できる? 光實こんにちは、公認会計士・税理士の光實(みつざね)です。 こんな悩みを解決 ...
②買い手が作成する仕入明細書
通常は売り手が買い手に請求書を発行しますが、仕入明細書は買い手が売り手に発行するものです。
ただ、適格請求書で求められている記載事項と売り手側の確認があれば、仕入明細書でも仕入税額控除が認められます。
仕入明細書の記載事項
仕入明細書上で求められている記載事項はこんな感じです。
①仕入明細書の作成者の氏名または名称(買い手側の情報)
②課税仕入れの相手方の氏名または名称および登録番号(売り手側の情報)
③取引年月日
④課税仕入れの内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤税率ごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額および適用税率
⑥税率ごとに区分した消費税額等
適格請求書は、売り手が発行して自身の登録番号を記載しますが、仕入明細書は、買い手が発行して売り手の登録番号を記載しないといけないので注意が必要です。
売り手側の確認を受ける方法
次に売り手側の確認を受ける方法も見ておきたいと思います。
売り手側の確認を受ける方法としては、仕入明細書へ「送付後一定の期間内に連絡がない場合確認済みとします」のような文言を入れて交付することも認められます。
その他、以下のような方法も認められます。
・仕入明細書などへ確認済みの署名等をもらう
・売り手とやり取りをするオンラインシステム上で確認機能を設ける
・電子メール等で確認した旨の返信を受ける
要するに、確認する方法に決まりはなく、売り手側が内容について確認できていることが証明できれば問題ないということですね。
③、④受託者から交付を受ける書類
本来、卸売業者や農協等に委託して販売する取引の売主は出荷者です。
出荷者(委託者)⇒卸売業者、農協等(受託者)⇒買い手
なので、出荷者が買い手に個別に適格請求書を発行することが原則です。
ただ、それを実際にやるのは困難なので、出荷者からの買い手への適格請求書の交付義務は免除されています。
交付義務の免除について詳しくは、こちらを参考にどうぞ。
-

-
適格請求書の交付義務が免除されるケースをわかりやすく解説します!
悩んでいる人 ・適格請求書の交付義務って免除されないの? ・適格請求書ってないとだめなの? ・免税事業者はどうなるの? 光實 こんにちは、公認会計士・税理士の光實(みつざね)です。 こんな悩みを解決で ...
ただ、その場合でも買い手は、受託者である、卸売業者や農協などから適格請求書を受領して保存しておく必要があります。
どのくらいの期間保存する必要があるの?
適格請求書等の保存期間は、受領した課税期間の末日の翌日から2月が経過した日から、7年間です。
例えば、個人事業主の場合、課税期間の末日は、12月31日なので、翌日は1月1日です。
そこから2ヵ月+7年間保存しておく必要があります。
これは、発行する側も同じで適格請求書を発行した事業者も適格請求書等の写しを保存する義務があり、保存期間も同様となります。
3万円未満の特例規定の廃止
現行制度では、「3万円未満の取引」や「請求書等が受領できなかったことについてやむを得ない理由があるとき」は帳簿の保存のみで仕入税額控除を認めています。
ですが、インボイス制度に変わるとこの規定は廃止されます。
なので、3万円未満の取引なども今後は適格請求書等が必要になると覚えておきましょう!
今まで少額取引についてクレジットカード明細を利用して仕入税額控除をしていた人も注意したい所です。
こちらで記事を書いていますので参考にどうぞ。
-

-
インボイス制度が始まると、クレジットカード明細は利用できない!?
悩んでいる人 ・インボイス制度が始まるとクレジットカード明細ってどうなるの? ・利用できなくなるの? ・利用できなくなったらどうすればいいんだろ? 光實 こんにちは、公認会計士・税理士の光實(みつざね ...
適格請求書等の保存がなくても仕入税額控除が認められるケース
3万円未満の取引などの特例はなくなるんですが、全てにおいて、適用できないケースもあります。
なので、ここでは、適格請求書等がなくても仕入税額控除が認められるケースを見ておきたいと思います。
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケース
一定の取引については、適格請求書等を入手することが困難な取引として、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認めらています。
①3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
②適格簡易請求書形式の入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除く)
③古物営業者が適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入(棚卸資産になるもの限る)
④質屋営業者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得(棚卸資産になるものに限る)
⑤宅地建物取引営業者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入(棚卸資産になるものに限る)
⑥適格請求書発行事業でない者からの再生資源および再生物品の購入(棚卸資産になるものに限る)
⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入
⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張費等(出張費、宿泊費、日当および通勤手当)
よくある取引としては、①3万円未満の鉄道やバスの利用、⑨出張に係る経費や通勤手当が該当すると思います。
なので、この部分はインボイス制度に移行しても、現行制度とあまり運用は変わらない所かなと思います。
簡易課税制度を選択している場合
簡易課税は課税売上高5,000万円以下の事業者に認められている簡易な消費税の計算方法です。
簡易課税は原則的な消費税の計算方法と仕組みが違います。
簡単に説明すると。
| 原則的な方法
売上で預かった消費税ー仕入で実際に支払った消費税=納める消費税 |
| 簡易課税
売上で預かった消費税ー見積もった仕入にかかる消費税=納める消費税 |
簡易課税の場合、売上で預かった消費税に一定の割合を乗じて、仕入にかかる消費税を計算します。
仕入にかかる消費税をざっくりと計算する感じです。
なので、簡易課税の計算では、仕入で実際に支払った消費税をつかいません。
そのため、適格請求書等の保存は、仕入税額控除の要件となっていません。
たとえば、免税事業者は適格請求書を発行できませんので、簡易課税ではない原則課税の事業者が免税事業者と取引をしても仕入税額控除をとることができません。
でも、簡易課税をとっている事業者だと、適格請求書等がなくても仕入税額控除ができます。
要するに、免税事業者と取引をしても影響を受けないというメリットがあります。
まとめ
まとめます。
ポイント
・仕入税額控除の要件は帳簿と適格請求書等の保存
・適格請求書等には、適格簡易請求書や仕入明細書なども含まれる
・適格請求書等の保存期間は、受領した課税期間の末日の翌日から2ヵ月+7年間
・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケースもある
・簡易課税を選択している場合は、適格請求書等は仕入税額控除の要件にはならない
・簡易課税を選択していると、インボイス制度へ移行しても免税事業者との取引で影響を受けない
今回は、インボイス制度における保存が必要な請求書等に焦点をあてて解説してみました。
まだインボイス制度が始まるまで時間がありますが、徐々に準備をしていく必要があります。
今後も解説記事を増やしていきますので是非参考にして頂ければと思います。